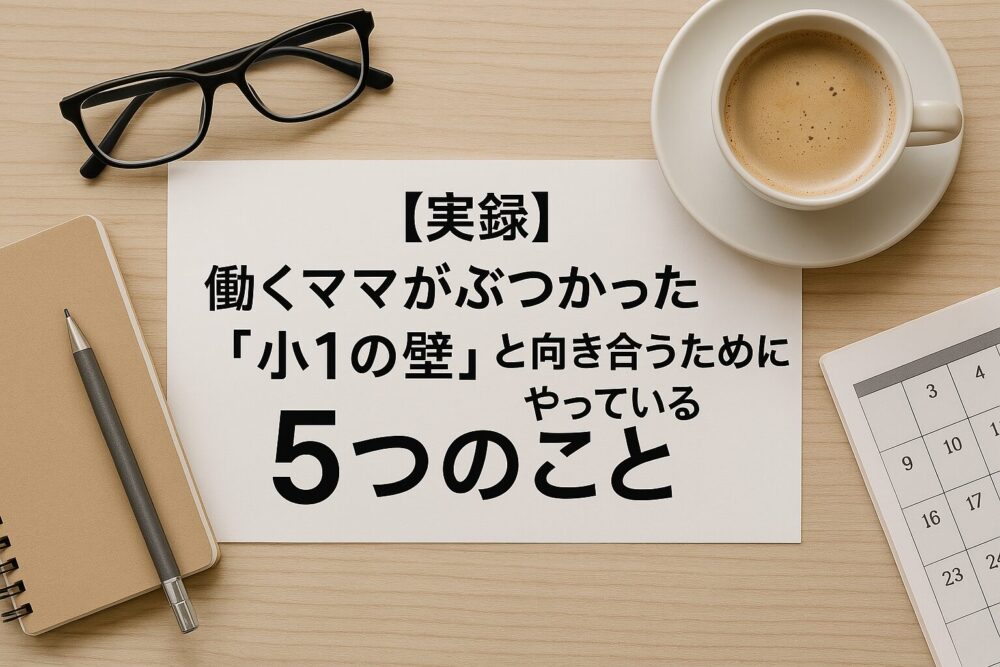「小1の壁」ってご存じですか?
子どもが小学校へ進学すると、それまでの保育園生活とは大きく環境が変わります。
時間割の変化や家庭でのサポートなど、親も子も新たな生活に適応するまでに戸惑うことも多くなります。
私自身も実際にその変化を経験し、「これが『小1の壁』か…」と実感したひとりです。
今回は、共働き家庭の母として、毎日の負担を少しでも軽くするために実践している5つの工夫をご紹介します。
共働き家庭にとって、小1の壁はリアルだった
今年4月、わが子がついに小学1年生に進学しました。
ドキドキしながら迎えた入学式。新しい生活がスタートしましたが、すぐにこう思ったんです。
「これが、聞いていた“小1の壁”か……」
朝の準備が思うように進まず、慌ただしい日々が続きました。
日によって変わる持ち物の準備も、親が一緒に確認しないと不安です。
学校が終わったあとは学童へ。夕方にはクタクタで帰宅する子ども。
そんな様子を見て、あらためて感じました。
子どもにとっても親にとっても、新しい生活リズムに慣れるまでは想像以上に大変。
これが「小1の壁」なんだと、実感する毎日が始まりました。
少しでもラクにするためにやっている5つの工夫
1. 持ち物チェックを“親子セットで”習慣化
学童の準備や連絡帳の確認など、朝のバタバタを減らすために、前日の夜に「持ち物チェックタイム」を一緒にやっています。
子ども自身に声を出して読み上げさせると、自分で覚える力もついてきて◎。私も「明日の準備できてる?」と毎朝聞かなくてよくなり、気持ちがラクになりました。
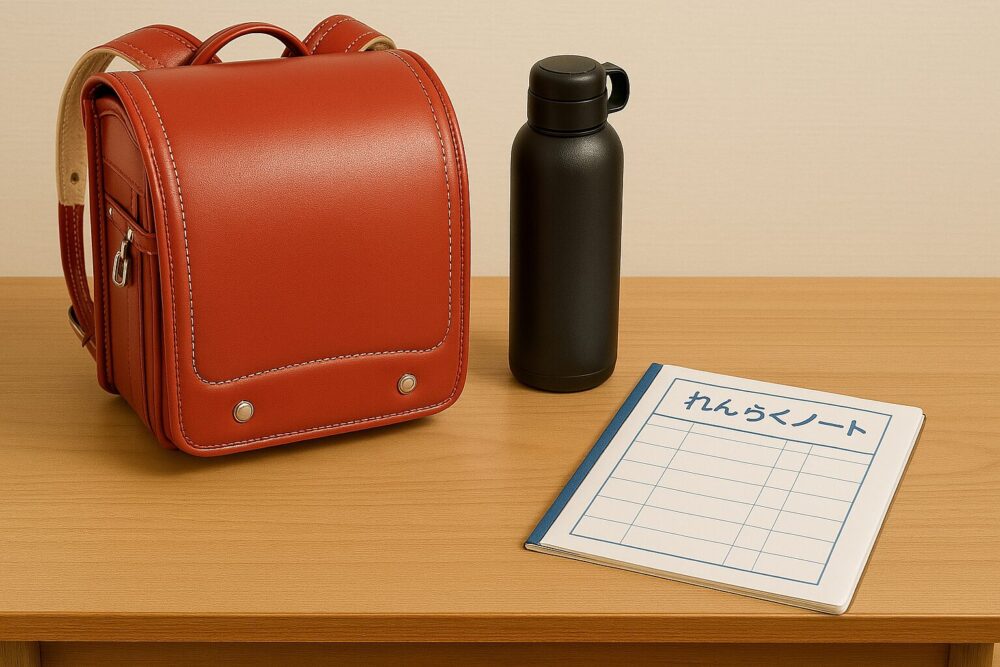
2. 平日の夜ごはんは“考えないメニュー”をスタメン化
「献立に悩まない」を目指して、月〜金はある程度ローテーションで回せる定番メニューを決めました。
たとえば、「月曜日はカレー」「木曜日は麺類」といったように、曜日ごとにざっくりとメニューを固定することで、毎日の「何作ろう…」というストレスがぐっと減ります。
手抜きに見えるかもしれませんが、家族の満足度は意外と高め。
食卓が安定すると、親も子も気持ちに余裕が生まれるなと感じています。

3. 学童から帰宅後のルーティンを整える
「ただいま」から「寝る」までが本当に長い。
だから、学童から帰ったあとは「お友達と公園で30分程遊ぶ(マンションの下の公園なので付き添いはなし)→お風呂→ご飯→スマイルゼミ→自由時間→歯磨き→就寝」という流れを決めています。
子どもも次に何をするかがわかっていると気持ちが落ち着くようで、以前よりスムーズに動ける日が増えました。

4. 「ちゃんとやらせなきゃ」を手放す練習中
「提出物は?」「忘れ物はない?」「宿題した?」と、つい口を出したくなることもありますが、最近は少しだけ我慢するようにしています。
失敗から学ぶことも大切だと考え、もしできていないことがあっても「じゃあ次はどうしたらいいかな?」と声をかけるようにしています。
私自身も「母親だからといって完璧でなくていい」と、少しずつ肩の力を抜く練習を続けています。

5. パパと情報共有アプリで「抜け漏れ防止」
学校からのプリントは写真を撮って、夫婦で使っている共有アプリにアップしています。
わが家では「TimeTree(タイムツリー)」という家族共有アプリを使っています。
予定を共有できて、学校行事の見落としが減ってかなり助かっています。
▶︎ TimeTree公式サイトはこちら
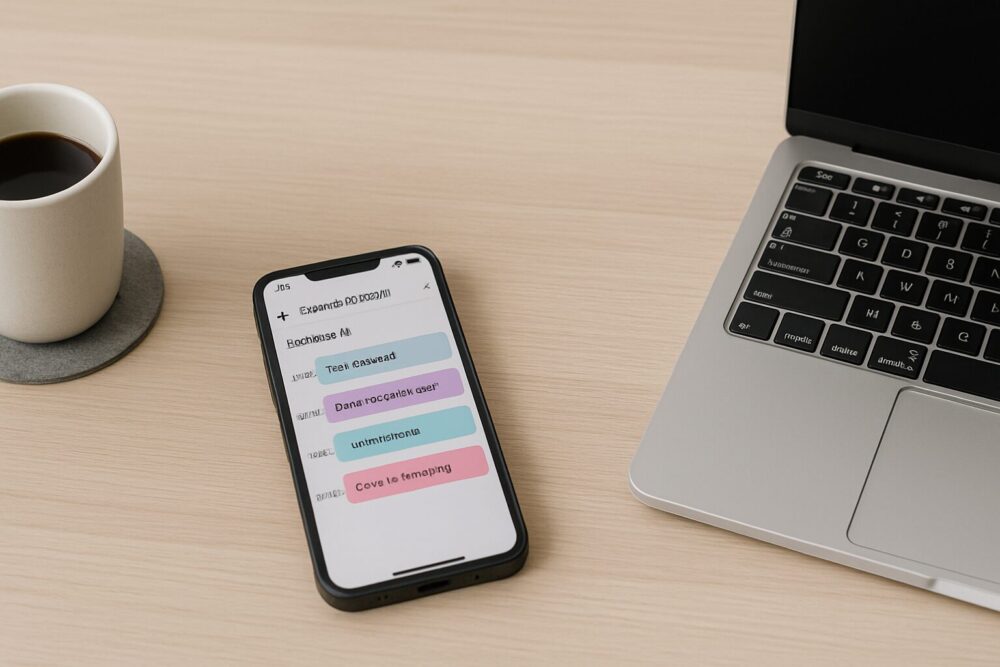
反抗期かもしれない…そんなときに心がけたい接し方
小学校に入学して数ヶ月。新しい環境に少しずつ慣れてきた一方で、「あれ?なんだか最近、反抗的?」と感じる場面が増えてきました。
いつもは素直だったのに、「今やろうと思ってたのに!」「もうわかってるってば!」と、言い返してくることも。
親としてはびっくりしたり、少し戸惑ったりしますよね。
でも実はこの変化、「成長の証」でもあるんです。
小さな「自分の気持ち」を主張し始めたサイン
子どもが反発するような言葉や態度を見せると、「これって反抗期?」と思ってしまうかもしれません。
でも、急にわがままになったわけではなく、「自分の意見」や「自分でやりたい気持ち」が少しずつ芽生えてきたサインでもあります。
例えば…
- ランドセルは自分で用意したい
- 選ぶ服は自分で決めたい
- 注意されるとムッとして黙ってしまう
こんな時は、頭ごなしに否定せず、まずは「そう思ったんだね」と子どもの気持ちを受け止めてあげることが大切です。
少しずつ自立していく過程で、親子の距離が揺れることもあるけれど、最後には「やっぱりここが安心」と思える家庭でありたいですね。
女の子の場合は、「可愛いね、今日も可愛いよ」と声をかけると、怒っていた顔がふっと和らいでニコッとしてくれることがあります。
我が家では「ママの宝物だよ」「いつでも味方だからね」と伝えるようにしていて、安心感を与えるために、スキンシップを多めに取ることもあります。
そうすると、うれしそうにこちらへ寄ってきて、スキンシップを返してくれることも増えてきました。
小さなやりとりですが、子どもにとっては「ここが自分の帰る場所」だと感じられる瞬間なのかもしれません。
イライラしないためのちょっとした工夫
反抗的な態度に毎回きちんと向き合おうとすると、親も疲れてしまいますよね。
私自身、「また反発された…」と落ち込んだこともあります。でも最近は、次のような小さな工夫で少し気持ちがラクになってきました。
- すぐに注意せず、まず深呼吸
- 子どもの言葉の「奥」にある気持ちを想像する
- できたことはしっかり認める
例えば、「自分で準備できたね」と声をかけるだけで、子どもも笑顔を見せてくれることがあります。
そうした前向きな声かけが、反抗の裏にある不安や緊張をやわらげる助けになることも。
完璧な親じゃなくていい。大切なのは「見守る心」
「反抗期にどう向き合えばいいのか…」と悩むこともあるかもしれませんが、完璧な対応をしなくても大丈夫。
大切なのは、「子どもなりの気持ちやペースがあること」を忘れずに、安心して戻れる場所を用意しておくことだと思っています。
まとめ|これから小1の壁に向かうママ・パパへ
小さな反抗も、子どもが一歩ずつ成長している証。
戸惑いながらも、子どもと一緒に親も成長していけたらいいですよね。
焦らず、完璧を求めすぎず、まずは今日一日を「がんばったね」と認めることから。
その積み重ねが、子どもの心を支える力になっていくと信じています。
もしこれを読んでいるあなたが、「うちも大丈夫かな…?」と不安に感じているなら、ぜひ知ってほしいことがあります。
大丈夫です。どの家庭も、バタバタしながら、少しずつ慣れていっている途中です。
子どもも親も、最初から完璧なんてできません。
疲れた日はお惣菜に頼ったっていいし、提出物を忘れてしまっても大丈夫。
無理しすぎず、手を抜けるところは抜きながら、ゆっくり進んでいきましょう。
「小1の壁」は、急に立ちはだかる“壁”というよりも、新しい生活の“坂道”のようなもの。
我が家もまだ登っている途中ですが、一歩ずつ子どもと一緒に歩いていけば、いつか必ず平らな道になるはずです。
焦らず、慌てず。
今は途中でも、きっと大丈夫。あなたのペースで、今日を大切に過ごしてくださいね。